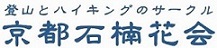石楠花登山教室「山へ行こう.2」
読図の基本
① 歩く前に地図を読み込んでおく
山に入る前に、地図情報(縮尺・等高線の混み方・凡例)から実際の地形を想像することと、現在地確認を行なうチェックポイントを設定しておくことの二つを行なっておく。ピークや鞍部(コル)、尾根や谷の分岐、斜度が急に変化する場所では現在地を確認しやすいので、そうした場所をチェックポイントにする。尾根の方向や、小ピークをいくつ通ったかということも手がかりになる。なお、現在地確認するときには、必ず複数の手がかりをもとに現在地を確認すること。
縮尺が2万5000分の1なら、地図上の1cmは250mである。このことを利用して、2万5000分の1の地形図で標高差50mごとにやや太い線で書かれてある等高線の間隔から、角度を計算したものを表1に示す。等高線の混み方だけで地形を想像するのは慣れるまで難しいが、表1を参考にすると地形を想像しやすくなる。
|
地図上の水平距離(mm) |
実際の水平距離(m) |
角度 |
|
2 |
50 |
45.0 |
|
3 |
75 |
33.7 |
|
5 |
125 |
21.8 |
|
10 |
250 |
11.3 |
|
15 |
375 |
7.6 |
|
20 |
500 |
5.7 |
|
50 |
1250 |
2.3 |
② コンパスを適切に使う
地図はコンパスと組み合わせて使う。以下の文章ではコンパスの使い方を説明する。最初に、図1に、最も一般的なシルバコンパス各部の名称を示す。シルバコンパスを指すことにする。シルバコンパスというのはシルバ社の商標だが、シルバ社以外のプレートつきのコンパス製品もシルバコンパスと呼ばれることが多い。
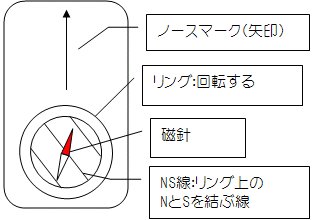
地図を使う際には、地図と周囲の地形を対応させる必要がある(これを整置、もしくは正置という)。地図と周囲の地形を対応させるとき、特徴的な地形・目印を使える場合はほとんどないので、通常はコンパスを用いる。
(1) コンパスは真北をささない:真北と磁北
まず、地図上の北とコンパスの針が示す北とは異なることを押さえておこう。磁石のN極は北を指すと小学生の頃に習ったと思うが、コンパスが指しているのは、真北(北極の方向)ではなく、磁北(カナダ・ハドソン湾の方向)である。地図の縦の縁(真北)に磁針を合わせるのではなく、磁北の方向に磁針を合わせないと正確に整置をしたことにならない。
真北と磁北のずれを偏角と呼ぶ。日本では偏角の大きさはおよそ西に4度から10度の間に入っている。偏角の大きさは、地図に「偏角は西偏*度」などと書かれているので使用前に確認しよう。
(2)磁北線を引く
コンパスを使って整置をするためには、地図にあらかじめ磁北の方向に直線を引いておくととても便利だ。この線を磁北線という。ほとんどのコンパスの取扱説明書では、コンパスのリングを分度器代わりに使う方法を紹介している。しかし、リングの径は正確に磁北線を引くには小さすぎる。大きめの分度器を用いるか、三角関数(タンジェント)と定規を利用した方がよい。タンジェントはエクセルなどの表計算ソフトを使えば簡単に計算できる。一本引いたあとは、上下の地図の縁に等間隔の目盛りをつけたり、定規などを使ったりして、平行な線を4~5cmおきに引いておけばよい。
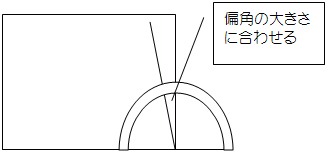
|
偏角 |
H(cm) |
|
5°00′ |
3.23 |
|
5°30′ |
3.56 |
|
6°00′ |
3.89 |
|
6°30′ |
4.21 |
|
7°00′ |
4.54 |
|
7°30′ |
4.87 |
|
8°00′ |
5.20 |
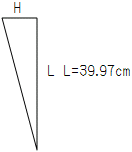
(3)コンパスを使って整置する
まずコンパスを地図の上に載せる。次にコンパスの針が磁北線と平行になるまで、地図を回転させる。これでおしまい。針の赤いほうが北になっていること。整置そのものには、磁針さえあればいいので、プレートがついていないコンパスでも同じように正確な整置ができる。周囲と地図を見比べてみると、地図上で描かれた方向に、実際の特徴物があることが確認できるだろう。
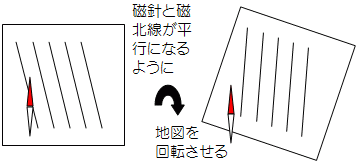
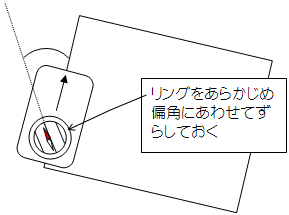
磁北線を引かないでも、地図の縦の縁とコンパスを使って整置できる。磁北線を引いていなかった場合、偏角の分だけ傾けた方向に磁針を合わせると整置できる。シルバコンパスの場合は、以下のようにやるとより正確にできる。ノースマーク(矢印)をあらかじめ偏角の分だけ進行線から傾けておく。進行線を地図の縦の縁に合わせ、磁針はノースマークに合わせると整置が完了する。
ただし、上記のように磁北線を引かないで済ます方法だと、進行方向や尾根の方向の確認しようとするときに不便なので、ルート上だけでも磁北線を引くことを勧めたい。例えば、進行方向を確認しようとするときには、コンパスを整置するために置いた縁のところから現在地のところに動かす必要があるが、コンパスを動かすときにせっかくの整置がずれてしまうのだ。
コンパスの使い方 2 : 方向の確認(地図からコンパスへ)
例えば、以下のような時に使う。
1. 現在地から次のチェックポイントまでの進行方向を確認したいとき。
2. 道が分岐しているときに、正しい分岐がどちらか判断するとき。
3. 自分のいる尾根が、思っている尾根か確かめるとき(尾根の方向を確かめるとき)。
4. 道の方向の変化から大まかな現在地を確認したいとき。
手順は以下のとおりである。
① まず、地図上の現在位置と目的地をプレートの長い縁に合わせる。ノースマーク(矢印)などコンパスに書かれている直線と合わせてもいいが、プレートの縁のほうがはるかに合わせやすいはずだ。合わせる方向は、コンパスのノースマーク(矢印)が、現在地から目的に向けて仮に引いた矢印と同じ向きになるようにする。
② リングを回して、リング上のNとSを結ぶ線(以下NS線)を磁北線と平行にする。(このとき磁針は無視する。)
③ コンパスを体の前面に持ち、コンパスを動かす。NS線と磁針が重なった時のノースマーク(矢印)が進行方向になる。
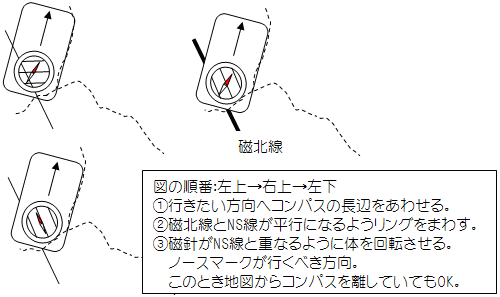
コンパスの使い方 3 : 方向の確認(コンパスから地図へ)
明らかに地図上の位置が分かる目標が見えるときに、道のない原野を直進するためや、
現在地確認するために用いる方法を紹介する。
① 地図上でその位置を知ることのできる塔や山を目標物とする。目標物に正対し、コンパスのノースマーク(矢印)を目標物へ向け、リング上のNS線と磁針を合わせる。
* リング上のNS線と磁針がずれないように気を付けながら、ノースマーク(矢印)の方に直進すれば、途中で目標物を見失っても目標物のところに出ることができる。現在地確認に使うには②~④の手順を更に踏む。
② セットしたままリングを動かさないようにに注意してコンパスを地図の上におき、プレートの長い縁を目標物に当てはめる。
③ 次にコンパスのリング上のNS線が磁北線と平行になるまで目標物を軸として回転させる。平行になったらコンパスのプレートの縁に沿って線を引く
④ あなたの現在位置は③で引いた線上のどこかにある。 ①~③の作業を別の目標物について行えば、あなたの現在位置は線の交わった所だと、特定できる。
「GPSの利用について」
測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成13年法律第53号)が今年4月に施行され、経緯度は世界測地系で表示することとなりました。当分の間は、一般の方の手許には、世界測地系で経緯度が表示された新しい地図と、日本測地系で経緯度が表示された従来の地図とが混在することになるので注意が必要である。
道迷いし易い状況の例
終バスに乗り遅れまいなどの焦り・雨水によって出来た溝が道に見える・認知地図(心の中の地形イメージ)の歪み・ルート入り口の見落とし・巻き道と間違えて尾根から外れる・誤った道標・方向確認を他人任せにする・初リーダー時や新人さんがいて,間違えたかもしれないと言うのがかっこ悪く思えるとき。
コンパスと地図による現在地確認をチェックポイントごとに行なっていないとき(条件によって異なるはずだが,一般に,山道で30分以上地図を開かずに歩いているときは,現在地確認が足りない場合が多いと言えるのではないだろうか)。
【推薦図書】
1. 村越真 2001 道迷い遭難を防ぐ最新読図術 山と渓谷社 ISBN4-635-20003-5 1700円
2. 平塚晶人 1998 2万5000分の1地図の読み方 小学館 ISBN4-09-366111-1 1600円
推薦図書1.は、道迷い遭難の原因分析および、地図からの情報読み取り・現在地確認・ルート維持の方法をとても丁寧に説明している。推薦図書2.は、練習問題が多い。文章の作成には、この他に、コンパスの取扱説明書、国土地理院HPなども参考にした。
◇ 地図が読めるメリットを以下に挙げておく。先が分かるから疲れにくい。どんな山行だったか思い出が良く残る。道も覚える。迷いながら歩く不安をあまり味わわないで済む。
◇ 地図を読めるようになるコツは,経験をつむのが一番である。そのために,ときにはグループを先導するのがいい(CLでなくとも)。2番目以降を歩いているとリーダー任せでついつい現在地確認を怠ってしまうし,先頭のほうが,視界をさえぎる他人の背中がない分,いろいろな情報を利用し易い。
(文責:橋口)